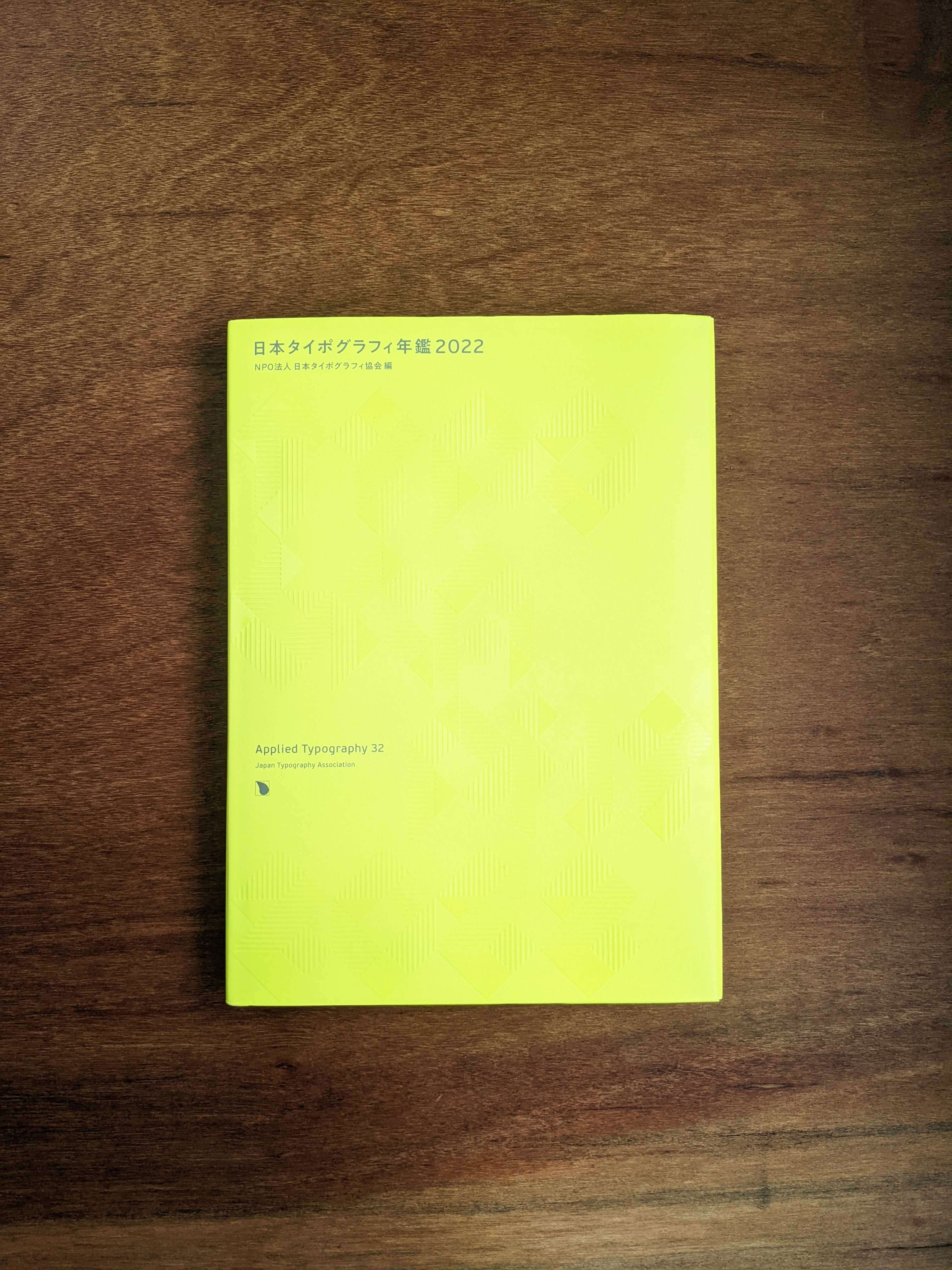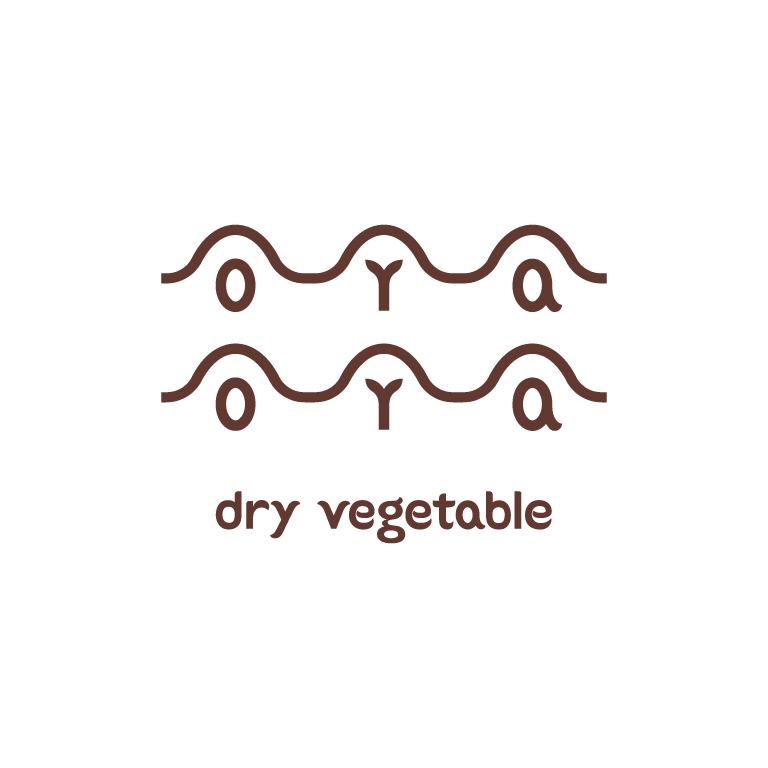展覧会「絵画と素描 Tableau&drawing-Four Sense-」
こんにちは、スタッフの山浦です。
曇り空が続いていますが道端で見かける紫陽花を見ると気持ちが明るくなります。
前回に引き続き、展覧会巡りの続きをご紹介します。
今回は、京都市役所前駅最寄りにある蔵丘洞画廊という画廊の企画展
「絵画と素描 Tableau&drawing-Four Sense-」へ行ってきました。
最も心惹かれたのは、日本画家の忠田愛さんの作品。
作品タイトル「星在るところ」


お猿の目がとても魅力的です。
次のこちらは出品作品ではないみたいですが
偶然、画廊の方が所蔵作品を出してくださっていたので観させていただきました。
作品タイトル「stardust」


ヘルマン・ヘッセの小説「デミアン」の話がふと頭をよぎります。
「観る」ということの醍醐味は、自分自身へ向けて会話ができることではないかと思います。
作品が作者から離れ、そして観賞者と出会うとき、絵を観る人によって作品はさまざまな人となり、語りかけをするのではないでしょうか。
忠田愛さんの描かれた人物を見つめると、自分自身を見られているような、見ているような、絵そのものに命を感じる不思議な感覚になります。
純粋に絵を観ることの幸せを感じた時間でした。
会期は今週の土曜日までみたいなので、
皆さんも、ぜひ足を運んで感じてみてください。
—
「絵画と素描 Tableau&drawing-Four Sense-」
2022年6月4日(土)~6月18日(土) 会期中無休
10:30-18:30
京都・蔵丘洞画廊
〒604-8091 京都市中京区御池通河原町西入 ホテル本能寺1F
—
また、忠田愛さんの個展が大阪吹田市のアートギャラリー、ippo plus(イッポ プリュス)にて開催されるようですので合わせて詳細ご案内いたします。
—
「いとおしいもの」
2022年7月16日(土)~7月25日(月) 会期中無休
12:00-18:00
ippo plus(イッポ プリュス)
〒565-0874 大阪府吹田市古江台 1-7-4
—
山浦